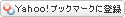相続放棄・限定承認・単純承認
相続放棄・限定承認・単純承認
相続の法的な3つの態様

相続が発生すると、残された遺産を分配するのですが、その前に、
法的には、相続の態様について次の3つの選択肢に分かれており、そのいずれかを選択することになります。
1.単純承認
2.相続放棄
3.限定承認
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継の対象となりますので、このような制度になっています。
相続開始後、原則、3ヶ月以内に選択しなければなりません。
1.単純承認
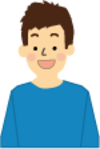
ごく普通にイメージする相続の態様で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。
単純承認には、これといった特殊な手続はいりません。
逆に、普通に遺産分割協議を行い遺産の分配を行うなど、相続人として相続するという行動をとれば、単純承認したことになります。
また、相続が発生した後3ヶ月間何もしなければ、単純承認したことになります。
通常の相続の場合、法律上の評価としては、みなさん、「単純承認している」ということになります。
2.相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、一切を相続しない態様です。
家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討すべきでしょう。
また、被相続人との関係が疎遠で被相続人の生前のことが全く分からないような場合で、かつ特に遺産の分配を受けるつもりがないというような場合にも、相続放棄を検討する価値はあると思います。相続放棄しておけば、万が一被相続人にそれまで分からなかった負債が出てきたとしても、債権者から請求を受けることはありません。
相続放棄をすれば、相続開始の時点から「相続人ではなかった」ことになります。
つまり、遺産分割協議を行う際には、相続放棄をした人を除いて、残りの法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。
原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
相続放棄の申し立てについても、お手伝いさせていただきます。
ときどき、「弟は相続放棄したから、遺産は全て兄の自分が相続する」というようなことを言う方がいらっしゃいますが、この「相続放棄」が、法律的な意味でいう「相続放棄」ではないことがよくあります。
つまり、家庭裁判所での手続きをしておらず、 単に「プラスの遺産を相続しないという意思表示があった」という意味で、相続放棄という言葉を使っている、ということになるのです。
この場合は、相続人の立場を失っているわけではありませんので、遺産分割協議の際には、相続人として参加しなければなりません。
また、もしマイナスの財産があれば、それを相続していることになりますので、注意が必要な場合があります。
3.限定承認
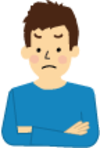
相続で得たプラスの財産の範囲内で、相続したマイナスの財産(借金)を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
プラス・マイナスの財産を清算し、マイナスの財産の方が多くなっても、その分を支払う必要がなくなります。
逆に、プラスの財産の方が多ければ、差引分の財産については取得することができます。
プラスの財産があるが、マイナスの財産もかなりあり、どちらが多いかはっきりしなかったり、あるいは、まだ他にもマイナスの財産が出て来る可能性があると思われるような場合に使われます。
限定承認の手続も、相続放棄と同じく、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
ただ、限定承認はあまり利用されていないようです。
というのも、手続きが面倒なことと、完結までに時間がかなりかかり、さらに、法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないからです。
また、税務上の問題もあるようです。
a:2675 t:2 y:3