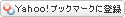遺言
遺言

遺言書を作成しておけば、ご自身の死後の遺産の相続について、誰がどのように相続するか、ご自身の意志によって定めることができます。
また、財産の分配に関することだけでなく、ご家族への思いを書いたり、葬儀の指示をしたりすることもできます。
ご自身の最終意思の表示です。
遺言による相続人の指定や相続分の割合の指定は、原則として、法定相続分よりも優先されます。(例外もありますが)
しかし、遺言が有効と認められるためには、法律によって定められた要件を全て充たすことが必要で、要件不備の遺言は無効となります。
作成の際には十分な知識と注意が必要です。
当事務所では、遺言作成のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
次のような事情がある場合には、遺言書を作成されることをお勧めします。
1.法定相続人が一人もおられない場合
⇒ご自身がお亡くなりになると、財産が国にいってしまう可能性が高いです。
2.子供がいらっしゃらないご夫婦
⇒相続人として、夫(又は妻)の親、あるいはご兄弟が登場します。
3.内縁の配偶者のおられる場合
⇒内縁関係である以上、相続権がありません。
4.再婚したが、前婚の配偶者との間に子供がいる方
⇒その子供にも相続権があります。
5.法定相続人の中に、行方不明者がいる場合
⇒行方不明者がいると、遺産分割の手続きに時間と費用がかかります。
など
遺言の種類
遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。(他に特殊な遺言もありますが、ここでは省略します。)
公正証書遺言
公正証書によって作成された遺言書が公正証書遺言です。
メリット
- 公証役場で公証人が作成に関与しますので、形式的な要件不備を理由に遺言書が無効になるという心配はありません。
- 作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、遺言書が偽造・変造される心配がなく、遺言書を紛失した場合には謄本の再発行をしてもらえます。
- 相続開始後、即座にその公正証書遺言書を使用して、相続手続きを行うことができます。(⇔後述の自筆証書遺言では「検認」の手続きが必要で、相続人にその手間をとらせることになります。)
- 文字が書けなくても遺言書を作成できます。
このようなことから、当事務所では、遺言を残される場合は、公正証書によることをお勧めします。
デメリット
- 公正証書を作成しますので、公証人に対する手数料が発生します。
- また、公正証書により遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要とされています。
証人2名をご用意いただくのが困難な方は、当事務所にご相談下さい。
自筆証書遺言
遺言者が自筆により作成した遺言書が自筆証書遺言です。
本文全文、日付、氏名を自筆し(パソコンでの作成は無効です。ただし、法改正により、遺産の目録はパソコン等で作成できることになりました。)、印鑑を押す必要があります。
メリット
- 自筆証書遺言は手軽に作成でき、また書き直しも自由にできます。
- 費用もかかりません。証人も不要です。
デメリット
- 形式の不備のために遺言が無効とされてしまったり、文章の表現方法に不備があって遺言者の希望どおりの相続が実現できないこともありえます。
- 偽造・変造や紛失の恐れがあります。
- 相続開始後、その遺言書を使って相続手続きを行う前に、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。(相続人の手間)
なお、検認の手続きについてはこちら
⇒遺言書を発見したら
このようなことから、当事務所では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。
秘密証書遺言
自身で書いた遺言書に署名・押印後、市販の封筒に入れて封印したものを公証役場に持参して、法定の手続きをしてもらったものが、秘密証書遺言です。
公正証書遺言と異なり、証人に内容を知られることなく、記載内容の秘密を保つことができます。
また、証人・公証役場により遺言の存在を確認できます。
しかし、遺言書の中身は自身で作成するため、その内容に関して、自筆証書遺言と同様の心配があります。
また、遺言の効力が発生した後に、家庭裁判所の遺言書検認手続を要することも自筆証書遺言と同様です。
a:2729 t:2 y:2